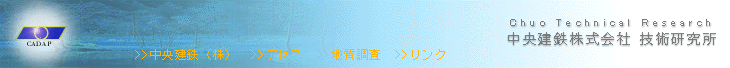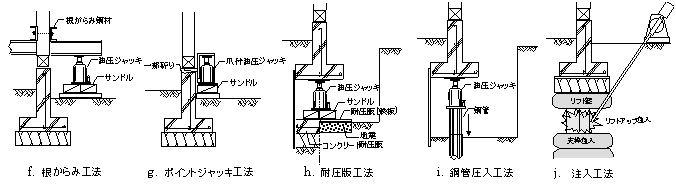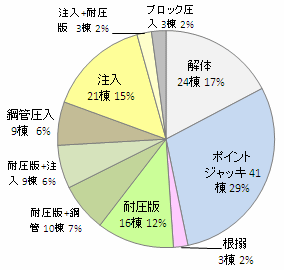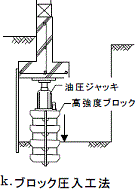| ≪CADAP≫ 被害予測システム | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
平成30年北海道胆振東部地震 このたびの地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申しあげます。 このたびの地震では地盤崩壊や建物の倒壊の他に、液状化により多くの住宅に大きな被害が生じました。 今後、沈下修正などの復旧工事が行われる事になると思われますが、これら復旧工事(主に沈下修正工事)における注意点について急ぎとりまとめましたのでご紹介致します。 当研究所では、日本建築学会「小規模建築物基礎設計指針」(以下「小規模指針」)の第10章「基礎の障害と修復」の執筆に携わり、この資料は東日本太平洋沖地震の液状化被害の復旧にも参考とされました。 復旧・復興支援WG「液状化被害の基礎知識」(日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議)
また、実際の復旧工事の実態調査を行い、その結果についてもご紹介致しましたが、未曾有の被害のなか、様々な問題点やトラブルがありました。
|
|||||||||||||||||||||
まとめ 復旧工事を検討するには、何れにしても、各沈下修正工法の特徴(特に短所)を良く理解して決める事が重要です。 住宅所有者の方は、専門知識のある方は少ないので、専門業者の説明に頼る事が多くなると思いますが、このようなサイトの情報を是非参考にして頂ければと思います。(当研究所は業者と利害関係がないので自由に書けます。) 今回の清田地区は過去にも液状化被害が見られている通り、液状化した地域は再液状化の可能性が十分にあります。 再液状化に際しての「再沈下の可能性」についての説明が「きちっと出来ない(しない)業者」は要注意です。 国や地方自治体の支援方針が決まると、その支援金を目当てに様々な業者がアプローチして来ると思います。 どの工法にも必ずリスクはありますが、そのリスクを説明せずに、単に「支援金の範囲で施工します!個人負担はありません!」等の説明に終始する業者は要注意です。 上記には各工法の一般的な長短所を示しましたが、特に注意が必要なのは「ポイントジャッキ工法」と「注入工法」です。 ポイントジャッキ工法では、ジャッキをセットするために基礎の一部を解体する必要がありますが、この際に、作業性を優先して、基礎の主筋(基礎の上側にある最も重要な鉄筋)を切断しても補強しないケースや、ジャッキアップ後に基礎と土台の間に端材を詰めるだけのケースが見られます。これらはモルタルで化粧して仕上がると外観的には分からなくなるので、特に注意が必要です。前者は鉄筋を切断しない、または必要な場合には十分な補強を行う、後者は所定の強度の台座を使用するか、鉄筋を配筋してコンクリートを打設するなどの対応が必要です。 また、注入工法は地中に薬液を注入するので注入状態やリフトアップの状況が直接確認できません。このため、薬液が敷地外に流出し、排水管を閉塞したり、隣の建物を隆起させてしまう事故が見られました。 施工実績が確かで、万一の場合の対応力がある業者の選定が重要と考えます。 不明な点があれば右上の「ご質問等」からお問い合わせ下されば、可能な範囲でお答えさせて頂きます。 |
|||||||||||||||||||||
.jpg) 基礎の主筋を切断しているケース |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| All Rights Reserved, Copyright(C) Chuo-Kentetsu Co.,Ltd | |||||||||||||||||||||